ページの先頭です
- ページ内移動用のリンクです
- ホーム
- IIJについて
- 情報発信
- 広報誌(IIJ.news)
- IIJ.news Vol.187 April 2025
- 東日本旅客鉄道株式会社 相談役 冨田 哲郎氏
社長対談 人となり 東日本旅客鉄道株式会社 相談役 冨田 哲郎氏
IIJ.news Vol.187 April 2025

各界を代表するリーダーにご登場いただき、その豊かな知見をうかがう特別対談“人となり”。
第31回のゲストには、東日本旅客鉄道株式会社 相談役の冨田哲郎氏をお招きしました。

東日本旅客鉄道株式会社
相談役
冨田 哲郎氏
1974年、日本国有鉄道入社。87年、東日本旅客鉄道株式会社入社後、事業創造本部担当部長、取締役総合企画本部経営管理部長、常務取締役総合企画本部副本部長、代表取締役副社長事業創造本部長、代表取締役副社長総合企画本部長等を経て、2012年、代表取締役社長、18年、取締役会長、24年より現職。
株式会社インターネットイニシアティブ
代表取締役 社長執行役員
勝 栄二郎
勝栄二郎は2025年3月末日をもって、代表取締役 社長執行役員を退任いたします。本記事内での役職表記は発行日時点のものです。
鉄道好きが高じて国鉄へ
勝:
まずは冨田さんの幼少の頃のお話をうかがいたいと思います。
冨田:
生まれは昭和26(1951)年で、東京のいちばん南、大田区蒲田で育ちました。すぐそばを東海道本線が通っていて、幼い頃から鉄道が好きだったので、自転車に乗って線路脇へ行って、ブルートレインを見るのが楽しみでした。夕方の5時から6時半くらいに、東京を出発する「さくら」「はやぶさ」「みずほ」といった寝台特急が走ってくるのです。それを眺めながら「これに乗れば、明日の朝、長崎、鹿児島、熊本へ行けるんだな」と想いを馳せていました。あまり遅くまで見ていると、母に叱られることもありました(笑)。
勝:
冨田さんは、どのようなご家庭でお育ちになったのですか?
冨田:
父親は東京ガスに勤めていました。母は専業主婦でしたが、結婚する前は小学校の教員をやっていたそうです。裁縫が上手だったので、母が縫ってくれたズボンや洋服を着ていました。
勝:
鉄道がお好きだったということは、旅行などもされていたのですか?
冨田:
旅行するほどの余裕はなかったので、時刻表をよく眺めていました。
勝:
ほお。
冨田:
時刻表を見ながら頭のなかで旅行するのです。空想なら、タダでどこへでも行けますからね(笑)。そんな子どもでしたから、就職先も迷うことなく国鉄を選びました。
勝:
ごく自然な選択だったのですね。
冨田:
鉄道は人やモノをある場所から別の場所に運ぶわけですが、そこにそれぞれの目的があったり、人生の転機があったりする。それらを支えていることに対し、大切な役割みたいなものを感じていました。
勝:
当時の国鉄は(入社するには)“狭き門”だったのでは?
冨田:
いえいえ、大学卒業が昭和49(1974)年で、オイルショックの直前でしたから、日本もまだ高度経済成長期で売り手市場でした。
勝:
当時の国鉄、今のJR東日本といえば、世界最大の鉄道事業者ですね?
冨田:
輸送人員では、おっしゃる通りです。
勝:
年間でいうと、どれくらいですか?
冨田:
年間約60億人、1日約1600万人といっていますが、これは往復の数なので、実数はその片道ご利用分の約800万人です。
地方勤務で経験したこと
勝:
最初は、地方へ行かれたりしたのですか?
冨田:
国鉄では、私のような東京出身者にはまず地方で経験を積ませることになっていたので、1年目は四国の高松で働いて、2年目に九州の鳥栖に行ったのですが、そこで大規模なストライキを経験しました。
ご記憶にあるかもしれませんが、昭和50(1975)年の11月末から12月にかけて、ストライキの権利を持っていない国鉄職員が8日間にわたりストを行なった「スト権スト」という前代未聞の出来事がありました。
ご記憶にあるかもしれませんが、昭和50(1975)年の11月末から12月にかけて、ストライキの権利を持っていない国鉄職員が8日間にわたりストを行なった「スト権スト」という前代未聞の出来事がありました。
勝:
ストライキなんて、今の若い人には想像できないでしょうね。
冨田:
そうですね。私はまだ2年目でしたから、労使交渉ができるほどの知識なんてなかったので、交渉している先輩のためにうどんを作って「がんばってください」と差し入れたりしていました。
3年目に東京に戻ってきて、国鉄と電電公社と専売公社が加入していた共済組合という組織の仕事に携わりました。当時、国鉄は年間、約1兆円の赤字を出していたのですが、共済組合も大きな赤字を抱えていて、その分は赤字の国鉄にさらに負担してもらっていました。鉄道が好きで入ってきたのに、そうした仕事をやることになって、どこか矛盾を感じながら働いていました。
共済組合で5年ほど働いて、昭和57(1982)年から国鉄を将来的にどうするのかという議論が始まった頃、今度は札幌に赴任しました。そこでは人事の仕事につき、団体交渉の矢面に立ちながら、労働組合の幹部と議論する日々を3年ほど過ごしました。現在、JR北海道の社員数は約6000人ですが、国鉄時代、北海道には約28000人の職員がいました。過剰な人員の処遇が問題になっていたのです。
いわゆる「合理化」を進めるという、どうにも元気が出ない状況でしたが、世の中にはさまざまな対立構造があって、議論を重ねながら物事が決まっていく――組織の内情を知って「いろいろ複雑だな」と思う一方、現場の職員が列車の安全運行と安定輸送のために日々尽力している姿を目の当たりにして、仕事への思いを新たにしました。
3年目に東京に戻ってきて、国鉄と電電公社と専売公社が加入していた共済組合という組織の仕事に携わりました。当時、国鉄は年間、約1兆円の赤字を出していたのですが、共済組合も大きな赤字を抱えていて、その分は赤字の国鉄にさらに負担してもらっていました。鉄道が好きで入ってきたのに、そうした仕事をやることになって、どこか矛盾を感じながら働いていました。
共済組合で5年ほど働いて、昭和57(1982)年から国鉄を将来的にどうするのかという議論が始まった頃、今度は札幌に赴任しました。そこでは人事の仕事につき、団体交渉の矢面に立ちながら、労働組合の幹部と議論する日々を3年ほど過ごしました。現在、JR北海道の社員数は約6000人ですが、国鉄時代、北海道には約28000人の職員がいました。過剰な人員の処遇が問題になっていたのです。
いわゆる「合理化」を進めるという、どうにも元気が出ない状況でしたが、世の中にはさまざまな対立構造があって、議論を重ねながら物事が決まっていく――組織の内情を知って「いろいろ複雑だな」と思う一方、現場の職員が列車の安全運行と安定輸送のために日々尽力している姿を目の当たりにして、仕事への思いを新たにしました。

分割・民営化を経て
勝:
北海道から、再び東京へ戻ってこられたのはいつですか?
冨田:
昭和60(1985)年です。東京では経営計画室に配属されました。国鉄改革にあたって国鉄側の取りまとめを行なう部署で、法案づくりなどをやりました。
勝:
大変な仕事だったでしょう?
冨田:
そうですね。毎晩、寝ない日が続きました。ただ、今、振り返ると「国鉄改革」自体が、本当に運が良かった。あのタイミングでしか実行できなかったと思うのです。
勝:
と言いますと?
冨田:
日本経済が絶好調でバブルの真っ只中でしたから、37兆円あった借金のうち22兆円を国が肩代わりしてくれた。年金も積立金が大幅に不足していたにもかかわらず、厚生年金に入れてもらえたし、約27万人いた職員のうち(分割・民営化後の)新しい会社で余剰人員とされた6万人の再就職先も国が面倒を見てくれました。本当にありがたかったです。
勝:
あの時は、国鉄を改革しようという、皆さんの熱意をすごく感じました。
冨田:
職員はそれぞれ一生懸命やっていたのですが、どこか空回りしていて、報われていない感じがあった。民営化されると倒産の可能性も生じるわけですが、逆に自分たちの力で未来を切り開いて新しいことに挑戦できる! というエネルギーが漲っていたのだと思います。
勝:
最終的に分割・民営化されたのは1987年でしたね。
冨田:
はい、そうです。当初は、まず黒字経営にしよう、お客さまへのサービスをもっと良くしよう、あともう1つ、絶対に事故を起こさない! というところから再出発しました。民営化されて自主的な運営ができるようになり、そうした当たり前の“健全経営”に取り組めるようになりました。
勝:
国鉄時代の赤字体質を脱却して、経営を黒字化できたいちばんの要因は何ですか?
冨田:
おもに2つあって、1つは、努力すれば黒字が出るかたちで新会社をスタートできたことです。国鉄の借金を引き継いでいたら、とても成り立たなかったと思います。
もう1つは、社員の熱量と言いますか、心のありようが変わったことです。いつも思うのですが、企業の力というのは、結局、社員のマインドなのです。特に鉄道のような仕事では、サービスを提供する社員がどういう気持ちでいるのかという点が非常に重要です。私は常々「安全は(守るものではなく)作るものだ」と言っていますが、社員一人ひとりのハートの状態が最終的に安全のレベルを決めます。そもそも元気でないと注意力も散漫になりますから、あらゆる意味でマインドが活性化したことが大きかったと思います。
もう1つは、社員の熱量と言いますか、心のありようが変わったことです。いつも思うのですが、企業の力というのは、結局、社員のマインドなのです。特に鉄道のような仕事では、サービスを提供する社員がどういう気持ちでいるのかという点が非常に重要です。私は常々「安全は(守るものではなく)作るものだ」と言っていますが、社員一人ひとりのハートの状態が最終的に安全のレベルを決めます。そもそも元気でないと注意力も散漫になりますから、あらゆる意味でマインドが活性化したことが大きかったと思います。

活力ある組織に成長
勝:
分割・民営化以降、節目となるような出来事はありましたか?
冨田:
最初の10年くらいは借金を返すことと黒字化することが最大の目標でした。それから徐々に設備投資ですとか、安全対策や地震対策へと転換していった。
ところが、ある時期、労使関係が少しむずかしくなって、高揚していた社員の気持ちがやや停滞したことがありました。労働組合も国鉄改革から10年くらいは協調路線を歩んでいたのですが、経営が黒字に転じてくると、労働者としての階級意識といったものが会社のなかに再び現れ始めたのです。
ところが、ある時期、労使関係が少しむずかしくなって、高揚していた社員の気持ちがやや停滞したことがありました。労働組合も国鉄改革から10年くらいは協調路線を歩んでいたのですが、経営が黒字に転じてくると、労働者としての階級意識といったものが会社のなかに再び現れ始めたのです。
勝:
なるほど。
冨田:
それで今から15年ほど前、もう一度、職場の活力を取り戻そうということで始めたのが「小集団活動」でした。
勝:
具体的にどういったものですか?
冨田:
社員自らが課題を提起し、その解決に向けてサークル(小集団)を結成して、メンバー同士の能力活用や相互扶助を促し、業務改善を図る活動です。
勝:
成果はありましたか?
冨田:
はい、変わりましたね。
私が会長だった頃の話ですが、大井町に大きな車両工場がありまして、そこへ行くと「新しいシステムを作りました」と言うので、「どんなシステムなの?」と尋ねたら、「電車のドアが故障した、冷房装置が故障した、トイレが詰まった、といった故障に関する情報を一元的に集約して、修繕の人間を手配するための仕組みです」と説明してくれました。私が「どこかに頼んだの?」と聞くと、「みんなで意見を出し合いながら、自分たちで作りました!」と。現場へ行くと、そういったことがあちこちで起こるようになりました。それ以外にも「これから地元の人たちと駅からハイキングするためのコースの打ち合わせをしてきます」など、積極的に外に向かう活動も増えてきて、ずいぶん変化してきたな、と思いました。
最近でいうと、新型コロナウイルスの影響でお客さまが減った時にも、サービス改善や安全対策や地域連携などについて、社員のほうからいろいろなアイデアが出てきました。新会社になってから令和7(2025)年3月で38年経ち、困難な状況を乗り越える力が社員にも備わって、分割・民営化された直後にあったような活力がまた戻ってきたな、と実感しています。
私が会長だった頃の話ですが、大井町に大きな車両工場がありまして、そこへ行くと「新しいシステムを作りました」と言うので、「どんなシステムなの?」と尋ねたら、「電車のドアが故障した、冷房装置が故障した、トイレが詰まった、といった故障に関する情報を一元的に集約して、修繕の人間を手配するための仕組みです」と説明してくれました。私が「どこかに頼んだの?」と聞くと、「みんなで意見を出し合いながら、自分たちで作りました!」と。現場へ行くと、そういったことがあちこちで起こるようになりました。それ以外にも「これから地元の人たちと駅からハイキングするためのコースの打ち合わせをしてきます」など、積極的に外に向かう活動も増えてきて、ずいぶん変化してきたな、と思いました。
最近でいうと、新型コロナウイルスの影響でお客さまが減った時にも、サービス改善や安全対策や地域連携などについて、社員のほうからいろいろなアイデアが出てきました。新会社になってから令和7(2025)年3月で38年経ち、困難な状況を乗り越える力が社員にも備わって、分割・民営化された直後にあったような活力がまた戻ってきたな、と実感しています。
地域社会のネットワーク形成
勝:
冨田さんが主導されて、ICカード乗車券「Suica」(スイカ)に電子マネーの機能を付加して、買い物にも利用できる仕組みを作られました。あれは非常に先見性のある事業でしたね。
冨田:
ICカードを乗車券として使い始めたのが2001年で、私がITビジネス部長だった2004年に電子マネーの機能を加えて、新たな事業展開を始めました。
最初は「使ってください」と営業に行っても、けんもほろろに断られました(笑)。リーダライタ(ICカードの読み取り端末)も非常に高価でしたからね。ようやく某コンビニエンスストアの特定店舗で試用していただけることになったのですが、しばらくはあまり反響もなかった。でも、時間が経つにつれて、支払いの際の手間も減らせるし、お客さまにも認知されて、だんだん広がっていきました。
最初は「使ってください」と営業に行っても、けんもほろろに断られました(笑)。リーダライタ(ICカードの読み取り端末)も非常に高価でしたからね。ようやく某コンビニエンスストアの特定店舗で試用していただけることになったのですが、しばらくはあまり反響もなかった。でも、時間が経つにつれて、支払いの際の手間も減らせるし、お客さまにも認知されて、だんだん広がっていきました。
勝:
実際に使ってみると、便利ですよね。
冨田:
ありがとうございます。我々が今、力を入れているのが「生活ソリューション」と呼んでいるサービスでして、Suicaなどを活用しながら、鉄道事業だけでなく、地域社会全体のデジタル化に資するネットワークを作っていきたい、と考えています。

鉄道の不思議な力
勝:
地域社会との結びつきということでは、2011年の東日本大震災のあと、鉄道がいち早く復旧していく様子を見て、地域づくりに鉄道は欠かせない存在なんだな、と感じました。
冨田:
あの時は、JR東日本の太平洋側のエリアで非常に大きな被害が出ました。私も被災地を見て回りましたが、気仙沼、陸前高田、石巻、釜石などは本当に悲惨な状況でした。最初は「これはどうにもならないな」と思いましたが、鉄道が復旧していくにしたがって、地域にも活力が蘇ってきました。
震災後、50日ほど経って、東京から青森まで新幹線が再び走り始めた時、沿線の皆さんが手を振ってくれたり、秋田新幹線が再開した際には「おかえりなさい こまち号」と書かれた横断幕を掲げてくださった。その光景を見て「鉄道には不思議な力があるなあ」と実感し、現場の社員も「運転していて、涙が出た」と言っていました。
震災後、50日ほど経って、東京から青森まで新幹線が再び走り始めた時、沿線の皆さんが手を振ってくれたり、秋田新幹線が再開した際には「おかえりなさい こまち号」と書かれた横断幕を掲げてくださった。その光景を見て「鉄道には不思議な力があるなあ」と実感し、現場の社員も「運転していて、涙が出た」と言っていました。
勝:
まさに鉄道が持つ“つなぐ力”ですね。
冨田:
小さな駅で開通式をやったりすると、「この町にこんなに大勢の人がいたのか」と思うくらい人が集まって歓迎してくれるのです。そういう経験があったので、社長・会長だった頃は、いつも社員に「地方・地域を大事にしよう」と語っていました。
勝:
素晴らしいですね。
技術を活用して地域おこしを!
勝:
これからJR東日本は、どのような方向性を目指しますか?
冨田:
2つ挙げるとすると、もっとも大切なのはやはり「科学技術の力」です。鉄道は技術サービス産業ですから、技術をベースとした価値を作ってサービスの質を上げていかなければならない。鉄道関連の技術といえば、わかりやすいのは「高速化」ですが、それだけでなく、列車の安全運行のための無線技術ですとか、準天頂衛星システム(みちびき)の活用ですとか、まだまだ可能性が残されています。さらに、エネルギー問題についても、我々自身、多くのエネルギーを使っている企業として脱炭素化を進めるために何ができるのか、真剣に考えなければならないでしょう。
2つ目は、先ほども話しましたが、地域・地方をもっと大事にする企業を目指すべきだと思います。JR東日本が地域を、街を元気にするという気概を持って、ハードやインフラだけでなく、デジタルの力、人間の知恵をめぐらせて、日本全体を豊かにするためのサービスが求められています。
地域おこしでこれから重要になるのが「インバウンド」です。ようやくコロナ禍から立ち直って、今年は4000万人を超えるインバウンドが見込まれていますが、それだけの外国人観光客を受け入れるにあたり、最大の懸案は“2次交通”が不足していることです。駅を降りても、バスが来ない、タクシーがいない……この現状どうするのか?
2つ目は、先ほども話しましたが、地域・地方をもっと大事にする企業を目指すべきだと思います。JR東日本が地域を、街を元気にするという気概を持って、ハードやインフラだけでなく、デジタルの力、人間の知恵をめぐらせて、日本全体を豊かにするためのサービスが求められています。
地域おこしでこれから重要になるのが「インバウンド」です。ようやくコロナ禍から立ち直って、今年は4000万人を超えるインバウンドが見込まれていますが、それだけの外国人観光客を受け入れるにあたり、最大の懸案は“2次交通”が不足していることです。駅を降りても、バスが来ない、タクシーがいない……この現状どうするのか?
勝:
いろんなものを“つなぐ”役割は本当に大切ですからね。
冨田:
おっしゃる通りです。2次交通の問題は他者任せにするのではなく、地域を盛り上げるために何ができるのか、自治体と一緒に我々も率先して考えて、実行すべきだと思います。
鉄道の仕事は「凡事徹底」
勝:
冨田さんの座右の銘を教えていただけますか?
冨田:
揮毫してほしいと頼まれた時に書いているのが「凡事徹底」です。これは社長になった時、ある新聞社の論説員の方から「冨田さんに贈る言葉」として教えてもらったものです。朝の挨拶とか、時間を守るとか、当たり前のことをやるという意味ですが、鉄道の仕事は、まさに「凡事徹底」なのです。
勝:
たしかにそうですね。
冨田:
「当たり前のことをバカにしないで、ちゃんとやる!」と、現場ではいつも言っていました。「凡事徹底」は、先ほど申し上げた「安全は守る(save)ものではなく、作る(make)もの」にも通じると思います。
勝:
最後に若い世代へメッセージをいただけますか。
冨田:
大変な時代だと思いますが、元気に頑張ってほしい、というひと言です。人口が減っているし、資源のない国だからこそ、もう一度、科学技術に目を向けて、デジタル化や脱炭素化の分野で日本ならではの競争力を発揮してほしいです。
勝:
今日は大変貴重なお話をうかがうことができました。ありがとうございました。
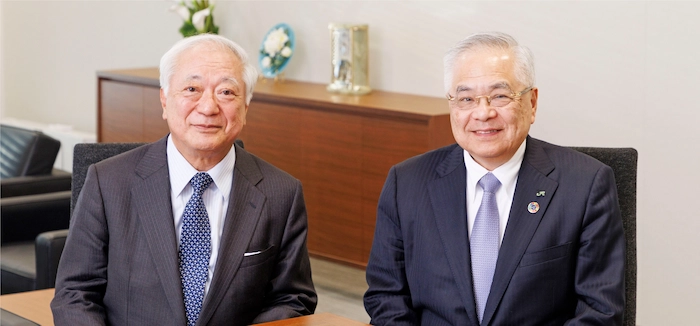
- 企業情報
- 情報発信
- バックボーンネットワーク
- 採用情報
ページの終わりです